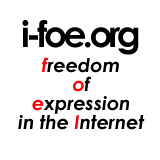準備書面(2005/07/15)
原告側準備書面
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
17年(ワ)第914号
原告松井三郎
被告中西準子
準備書面(1)
2005年7月15日
横浜地方裁判所 第9民事部合議係 御中
原告訴訟代理人 弁護士 中下裕子
同 弁護士 神山美智子
同 弁護土 長沢美智子
同 弁護士 中村晶子
記
第1 被告の主張に対する反論
1 第1項の主張について
一股に、他人の学説等について、学問的見地から批判する自由があることは当然のことであり、そのことは、原告も訴状において述べたとおりでおる。問題は、被告の本件行為が果たしてそのような「学問的見地からの批判」たり得るか否かである。被告の本件名誉毀損行為は、以下に述べるとおり、他者の発言を碌に聞かず、事実も十分に確認せずに、自らの勝手な思い込みまたは自ら創作した事実に基づいて、一方的に他者を非難し、その名誉・信用を貶めるというもので、およそ「学問的見地からの批判」とは似て非なるものである。さらに、被告は、本件名誉毀損行為後、原告の抗議により一旦は自己の非を認め本件記事を削除したにもかかわらず、本件訴訟を提起されるや、態度を一変させ、原告に対する事実無根の名誉毀損に他ならない本件行為を「学問的批判」であるなどと豪語し、それを前提にして、原告が「そのように批判されたことに憤慨して、それを「名誉毀損」などと評価して金銭的請求をするなどということは、およそ学者・研究者としての立場をわきまえないものである」などど主張し、またしても原告の名誉を傷つけているのである。
他者に対して事実無根の批判を行って、その名誉を毀損しておきながら、提訴されると、今度はそのような違法行為が「学問的批判」であるなどと言い逃れをし、そればかりか、侵害された名誉の回復を求めて正当な権利を行使している原告に対し、「学者・研究者としての立場をわきまえない」などと非難するのは、およそ筋違いも甚だしい?このような被告の態度は、学問に名を借りて自己の責任を回避しようとするもので、およそ真理追究の徒である科学者にあるまじきものである。
言うまでもなく、学問的批判の重要性は、批判によって自らを省み、自己修正を重ねることによって学問的水準の向上が図られることにある。被告のように、自らの行為を客観化して自己反省もできない人間には、およそ真の学問的批判など不可能であると言わざるを得ない。
2 第2項、第3項の主張について
被告は、甲第1号証は学者の立場から、原告のナノ粒子の有害性についての問題提起のあり方を批判するものであったとし、「新聞は、往々にして、ニュース性のあるものを優先して、しかも刺激的な見出しを付けて掲載するのであるから、センセーショナルな見出しのついた記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて、問題があるような話をするなどということは、参加者に誤った印象を植え付ける危険性が高く、専門家としてのプレゼンテーションとしては適切でない」と主張する(下線原告代理人)。
このような被告の批判は、原告が「センセーショナルな見出しのついた新聞記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて、問題があるような話をする」ことが前提となっている。仮に、原告が新聞記事を掲げてプレゼンテーションをしたとしても、専門家としての判断を加えた上でのことであれぱ、被告の批判は合理的な根拠を欠く。
本件においては、原告のプレゼンテーションは、決して「専門家としての判断も加えず、新聞記事をそのまま掲げて問題があるような話をした」ものではない。したがって、被告の批判は全く的外れで、合理的な根拠を欠く。被告自身、第3項においては、「本件で、原告が、新聞記事を掲げて、それを切り口として用いてナノ粒子について発言したことは事実である」と主張するのみで、「原告が専門家としての判断を加えずにそのまま掲げた」事実についての主張が欠落している。言うまでもなく、専門家としての判断を加えた上で新聞記事を掲げたか否かは、科学者としての信用にかかわる極めて重大な事実である。その部分の主張、立証抜きに、「学問的批判の自由」という被告の抗弁が成り立たないことは明らかであって、被告の主張はそれ自体失当である。
そもそも、「新聞は、往々にして、ニュース性のあるものを優先して、しかも刺激的な見出しを付けて掲載するのであるから、センセーショナルな見出しのついた記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて、問題があるような話をするなどどいうことは、参加者に誤った印象を植え付ける危険性が高く、専門家としてのプレゼンテーションとしては適切でないとの被告の見方自体も、極めて一面的なものと言わざるを得ない。新聞報道においては、記者はもちろん客観的な事実に基づくものであるよう常に心がけて取材を行っているうえ、記事になるまでには客観的事実に基づくものかどうかの観点から二重三重のチェツクが行われている。その上で、さらに意見が対立しているような場合には、偏った報道を回避するために、異なる立場からのコメントを掲載するなどして公平性に配慮されているのである。もちろん、中にはオーバーランしたものも見受けられるが、総じて客観的事実に基づき公平性に留意した報道がなされているといえるのである。彼告の新聞に対すろ批判は、あまりにも一面的な見方と言わざるを得ない。被告は、それをあたかも全体的な問題であるように主張することにより、まるで新聞が日常的に不当な報道をしているかのような印象を与えかねず、これは新聞報道関係看に対するいわれなき批判に他ならない。このような被告の新聞批判の手法を見ると、一部にしかあてはまらず全体論とLては誤った事実に基づいて、一方的に他者を批判するというもので、本件名誉毀損行為の手法と全く共通するものであることがわかるのである。事実に基づかずにセンセーショナルな批判を行っているのは、むしろ被告自身なのであって、新聞批判を口にする前に、被告こそ自らの言動を客観化し、自己反省に努めるべきである。
第2本件名誉毀損行為をめぐる事情
1 文科省特定領域研究¢内分泌撹乱物質の環境リスク
原告は、平成13年度から同15年度まで、文部科学省の特定領域研究「内分泌撹乱物質の環境リスク」の代表を務めた。この研究は、医学・薬学・理学・農学・工学の垣根を超えて、内分泌撹乱物質(いわゆる環境ホルモン)のリスクの学際的研究を目的としたもので、ノーベル賞受賞者の野依良治教授(当時は授賞前)がこうした研究手法を評価されたことから、研究活動が認められたものである。被告は、文科省の指名により、平成13年度の計画研究と公募研究の審査委員(主査)を務めていた?したがって、被告は、当初から原告の研究対象やその成果について十分認識していたのである。
3ヶ年にわたる研究の結果、100名近い新分野の博士号取得者を輩出するとともに、国際的な面においても、内分泌撹乱物質研究レべルを大きく前進させることができたとして、この研究は文科省最終評価委員会においても高く評価された。原告は、この3ヶ年の研究成果の概要を示す研究発表論文集や文科省に提出した書類一式を被告宛に送付していたものである。したがって、被告はおそらくこれら書類に目を通していたものと思われる。
2 環境省主催の国際シンポジウムの経過
(1)平成16年12月15日〜17日、名古屋市において、環境省主催の「第7回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム」が開催された。その中の第6セッションはテーマが「リスクコミュニケーション」で、被告はそのセッションの座長を務めていた。同セッションのパネリストは、原告の他、吉川肇子氏(慶應大学)、山形浩生氏(評論家・翻訳家)、日垣隆氏(評論家)、木下富雄氏(甲子園大学長)であったが、環境ホルモンのリスクコミュニケーションがテーマであるにもかかわらず、パネリストの中で環境ホルモン研究の専門家は原告だけという状況であった。
(2)シンボジウムに先立って、平成16年11月中旬頃、原告は、当日の発表のアブストラクトを提出した。すると、同年11月27日頃、被告から原告宛にメール(甲1の3)が届き、アプストラクトの内容は被告の期待するものとかなり外れていること、当日は内分泌撹乱物賃の性質や環境動態の解説は省いて、リスクコミュニケーションと学者の役割について原告の考えを述ぺてもらいたいことなどが記載されており、「今のままですと、むしろ先生にとってもマイナズになるような気がします」旨、書き添えられていた。原告は、このように強引に自分のやり方を押しつけてくる被告の姿勢に強い違和感を覚えたが、当日のディスカッションの円滑な進行には協力するべきであると考え、被告の希望に沿う形で準備する旨返答した。しかし、環境ホルモンの専門家が原告一人であることから、原告としては、他者が言及しないのであれぱ、その分野の研究がどこまで進んでいるのかを紹介した上で自分の意見を述べた方が、聴衆にもわかりやすいのではないかと考えた。そこで、原告は、「討論者は、内分泌撹乱物質の問題の専門家が少ないのが気になります」と書き添え、暗にそうした趣旨を被告に伝えておいたのであった。
(3)シンボジウム当日、各パネリストが15分間の意見発表を行った後、会場の参加者を交えて意見交換が行われた。原告の発表の概要は、甲第8号証のスライド及ぴ口頭説明の概要のとおりである。原告は、環境ホルモン研究については、「わからないことがいかに多いかということがわかった」旨の環境省の上家課長の言葉を引用したうえ、自らの研究によって明らかになったダイオキシンの毒性機構の基本的メカニズムを説明し、さらにそれは、ナノ粒子の毒性メカニズムとも共通性があるのではないかとの懸念を指摘した。そして、科学者は、生命の秘密に触れて自分達がいかに無知であるかを知っていること、科学者の役割は、「無知」を「理知」に変える努力をすることであること、内分泌撹乱物質の研究でわかった重要な点は、化学物質の影響を様々なエンドボイント(影響結果指標)で見ることができるということで、「発ガン性」や「死」だけがエンドボイントではなく、「全き姿で生まれてくる新しい生命」を保障することも科学者の責任であることなどの意見を述べた。その中で、原告は、ナノ粒子についての京都新聞の記事(甲8の第13図)のスライドを示したが、それは、原告らの研究成果からダイオキシンの毒性機構が判明しつつあるところ、そのメカニズムは有害性が懸念されるナノ粒子と共通性を持つことが推定されることを原告独自の見解として指摘したものである。したがって、本件ホームページの記事にあるように、原告が「要するに環境ホルモンは総わった。今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう」という趣旨で発言したことはなく、また、原論文を読まずに新聞記事をそのまま示して、ナノ粒子の有害性について説明したという事実もないことは明らかである(甲8、甲9)
このような原告の意見発表に対して、被告からも、他のパネリストや会場からも、一切批判はなかった?後に被告がホームページ上で行った批判は、この場では一切述べられていなかったのである。パネルディスカッション終了後も、被告から原告に対し、意見発表の仕方がまずいなどの指摘は一切なされていない。
3本件名誉毅損行為とその後の被告の対応について
(1)その後、被告と原告の間では何らのやりとりはなかったが、平成17年1月17日頃、原告は、知人の研究者からの知らせで、はじめて被告の本件ホームページ記載の事実を知った。そこで、直ちに記事を読んだどころ、訴状記載のような原告に対する事実無根の誹謗中傷が行われており、大変驚くとともに、このような、およそ科学者にあるまじき被告の行為を断じて許してはならないと強く思った。そこで、原告は、直ちに抗議のメール(甲3)を被告に送付した。
本件ホームページの記事のうち、原告に言及した部分の記述が、当日の原告の発表内容とはおよそかけ離れたものであることは、甲第8号証と対比すれば明らかである。このことからも、本件ホームページの記述がいかに被告の独善的見解に基づいたものであるかがうかがわれるのであるが、甲第2号証の記載からも明らかなように、本件ホームページの記述については、原告のほかにも2名からクレームが寄せられたのである。原告に関する記述については、まず原告の肩書きから誤りがあるうえ、「環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である」などと原告が全く発言していないようなことを、さも、そのような趣旨で発言したかのように記載されている。さらに、そのナノ粒子の有害性について、原告が原論文にもあたらず新聞記事だけを見せて問題であるような話をしたかのように記載されているのであって、全体的に原告に対する侮辱に溢れた記述となっており、原告の名誉を著しく損なうものである。これらの記述が事実に反するものであることは、甲第8号証、同9号証からも明らかである?原告の発言の趣旨は、環境ホルモン問題は終わったどころか、むしろ大変複雑な問題であるが、人や生物の生命活動に影響を及ぼす重大な問題であり、科学者としてその解明に向けてなお一層の努力が求められていることにあったのである。また、原告がナノ粒子の有害性に言及したのも、環境ホルモンのひとつであるダイオキシンの毒性機構の研究成果から、そのメカニズムの共通性を推定したものであって、決して環境ホルモン問題が終わったとの認識を示したものではなく、むしろ逆にその研究の重要性を指摘したものである。
(2)このようなことは、「内分泌撹乱物質の環境リスク」研究の審査委員を務め、原告を含む多くの論文を読んでいたであろう被告には、十分わかっていたはずである。また、シンポジウムに先立って原告が提出したアブストラクトを読み、当日、原告のプレゼンテーションを聴いていたならぱ、原告の発言の趣旨は、被告には容易に理解できたはずである。もし、聴きそびれた場合でも、シンポジウムの後で直接原告に確認さえすれぱ、すぐに事実を把握できたはずである。つまり、被告は、セッションの座長であるにもかかわらず、原告のプレゼンテーションをほとんど聴いていなかったか、聴き流したか、聴いていても理解できなかったか、もしくは意図的に論旨を変更して記述したのかのいずれかであることは明らかである。いずれにしても「科学者」にあるまじき態度であって、到底「学問的批判」などと言えるような事案ではない。
仮にも学問的批判というのであれば、なぜ、原告の反論の機会のあるシンボジウムの場で批判しなかったのか。仮に、その場でできなかったとしても、なぜ、その後、原告本人に対し直接、口頭又は文書で批判しなかったのか。もし、そうしてさえいれぱ、原告はその場ですぐに前提事実が全く違っていることを指摘して反論することにより、容易にその名誉を回復できるとともに、被告も自らの独善的批判の過ちに気づき、自己反省できたのである。そのような双方向のやりとりこそ、学問的批判の自由と言うべきであろう。なぜ、被告は、そのような双方向のコミュニケーションが保障された場ではなく、一方的な表現媒体であるうえ、他者によるチェックが全く働かない自己のホームページ上で批判したのであろうか。被告がわざわざ自己のホームページという媒体を選択したのは、学問の進歩に寄するというよりも、むしろ原告に対する批判を自己のホームぺージにアクセスする不特定多数の読者に知らしめる目的であったと思わざるを得ない?そのような被告の手法からも、本件がおよそ「学問的批判」とは程遠い、悪質な名誉毀損行為に他ならないことは明らかである。
(3)このような原告の抗議を受けて、被告は、翌1月18日付で、原告に対し、「件のホームページを削除しました?後日、おちついてから、もう一度お返事します。ご迷惑をおかけしました。」というメール(甲6)を送付した。そして、1月20日付で、「謝罪」とのタイトルの下に本件記事が削除された(甲2)。しかし、そこには、「おニ人の方から抗議がありました。・・・1に関しては、確かに私の非があると思いました」と記載されているのみで、原告に対する名誉回復措置は何ら講じられていなかったし、原告の抗議文も掲載されていなかったのである。このような被告の対応からは、「謝罪」とのタイトルを掲げてはいるものの、被告には真摯な反省態度が欠如していると判断せざるを得なかった。そこで、原告は、自らの名誉回復を求めて、本件提訴に踏みきったものである。ところが、本件答弁書では、被告はこのような「謝罪」の姿勢さえ一変させ、自らの過ちを棚上げにして、「学問的批判」であるなどど、学問に名を借りた自己責任回避を図ったうえ、正当な権利行使である原告の本件提訴まで、学者・研究者の立場をわきまえない不当訴訟であると主張し、再度原告の名誉を毀損する行為を重ねていることは既述のとおりである。このような被告の姿勢からは、到底反省の態度は窺えず、このままでは被告が自らのホームページ等で同様の名誉毀損行為を繰り返すことは容易に推察されるのであって、それを未然に防止する意味でも、速やかに被告の責任を認める判決が下されるべきである。
以上