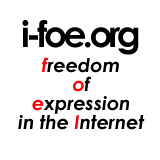準備書面(5)(2007/02/02)
原告側準備書面
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
丸に数字は文字化けするので、1)、2)などに置き換えた。
平成17年(ワ)第914号・平成17年(ワ〉第3375号反訴
原告(反訴被告) 松 井 三 郎
被告(反訴原告) 中 西 準 子
準備書面(5)
2007年2月2日
横浜地方裁判所 第9民事部合議係 御中
原告(反訴被告)訴訟代理人弁護士 中下 裕子
同 弁護士 神山美智子
同 弁護士 長沢美智子
同 弁護士 中村 晶子
記
証拠調べの結果を踏まえ、被告の準備書面5への反論を含めて、これまでの原告の主張を整理、補充する。
第1 本訴請求について
1 現代社会における名誉保護の必要性
(1)情報社会と名誉毀損問題
情報化・大衆化が急速に進行する現代社会においては、人の実体よりも人の外部的な評価・印象がより重要な役割をもつようになっている。現代社会では、1)名誉・信用に関する情報の価値が高まっていること、2)情報の伝達・利用の手段が多様化し、拡大していること、3)人の名誉等の情報に依存する聖範囲が拡大していること、4)名誉毀損等の情報侵害の目的が容易に達成され、情報侵害による効果が容易に得られること、5)名誉毀損等の情報侵害を大規模に行うことが可能になったこと、6)社会全体が覗き趣味の傾向が強まってきたこと等から、新たな態様・類型の名誉毀損等の問題が生じてきているといえる〔升田純『名誉毀損・信用毀損の法律相談』(青林書院)4〜5頁〕。
特に、IT技術の進展によって、誰もがインターネットを利用して、世界のどこからでも情報を入手できるようになっただけでなく、自由に全世界に発言ができるようになった。このことは、人々に計り知れない利便をもたらすと同時に、名誉毀損やプライバシー侵害という面で、これまでにない多くの問題を投げかけるようになったのである。
例えば、誰かがホームページ上で他人の名誉を毀損する表現をしたときには、その情報は瞬時に世界中に伝わり、莫大な損害を発生せしめる虞がある。しかも、これに対しては、新聞・雑誌・テレビなどの従来のメディアと違って、デスクや編集者などのような、予めチェックする手段がなく、少なくともしばらくの間は、無制約な情報が流通するのである〔五十嵐清『人格権法概説』(有斐閣)101〜102頁〕。
(2)名誉毀損と言論(表現)の自由
名誉毀損がこうした新聞・雑誌やホームページ等の記事によって行われるときには、名誉権の保護と表現の自由とが衝突することになる。周知のとおり、言論(表現)の自由は、精神的自由の中心的な基本権として憲法第21条で保障されている。他方、個人の名誉も、個人の尊厳と密接不可分な人格権として法的に保護されるべきものであり、確実な資料、証拠に基づかない表現によって他人の名誉を傷つけることは許されないことは当然である(最大判昭44.6.25など)。
そもそも、人は、自分が社会的に承認され得る存在だという確信を持つことができて初めて、社会において自由に行動することができるのである。自分が承認され得るという確信を持つことができないような社会では、人は、「行動しよう」とか、「挑戦しよう」というエネルギーを喚起できないであろう。社会における自由な行動や試行錯誤は、このような確信を背景にして初めて可能だといえる。このため、自分の価値を認めてもらい得るという確信を保障することが、人のあらゆる自由を保障することにつながる。したがって、社会的評価をむやみに低下させるような事態を許さないこと、つまり名誉毀損を許さないことは、個々人の自由を保障するための不可欠の前提だともいえるのである。その意味で、名誉権の保護と表現の自由とは決して対立するものではなく、名誉権の保護は表現の自由の保障の前提をなすものなのである〔佃克彦『名誉毀損の法律実務』(弘文堂)4頁、奥平康弘・宮台真司『憲法対論一転換期を生き抜く力』(平凡社)69頁〕。
(3)裁判所の役割
前述のような大衆化・情報化した社会において、表現の自由の濫用である名誉毀損行為の氾濫を防ぐために、裁判所の役割は極めて重要である。IT技術には光と影がある。IT技術には、多様な利便性があり、民主主義の発展に大いに寄与するものであるが、他方で、使い方を間違えると、品位のない誹誇中傷の類いの応酬が激化し、時にはそれを契機とした殺傷事件の発生にもつながりかねない。日本の社会が、IT技術を使いこなし、情報交流やコミュニケーションを通じて民主主義を成熟させることができるようになるには、徒に名誉毀損行為が繰り返されることのないよう、適正かつ節度ある言論のあり方について、裁判所が明確なルールをさし示すことが強く求められているのである。
2 本件名誉毀損行為について
本件名誉毀損行為は、個人のホームページ上の言論にかかわるものである。本件ホームページは、掲示板やフォーラムなど各人が自由な発言をすることができるものではなく、その意味では、名誉毀損の態様は、従来の新聞・雑誌などのメディアによる場合と共通性がある。しかし、他方、本件ホームページは、新聞報道のように、報道機関が取材活動に基づいて、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するというような高い公共性・公益性を持つものではなく、新聞・雑誌のようなデスク・編集者などの事前のチェックシステムを備えていないという特質がある。この点は、名誉毀損の免責性を考える上で、新聞・雑誌などのメディアに比して、より厳格な判断基準が求められるといえる。
新聞・雑誌などによる名誉毀損はその媒体を手に取った人にしか伝わらないし、テレビによる名誉毀損行為は原則として一回性のものであるが、ネット上に掲載された名誉毀損情報は違う。ある人が、本件被告ホームページの記事の存在・内容を全く知らずに、単に原告の業績・研究内容を知りたいと考えてgoogleやyahooなどの検索エンジンを用いて「松井三郎」「京都大学」などのキーワードを指定して検索をしたとする。すると、その人は、求めていた原告の業績・研究内容の情報だけでなく、検索画面に並んで表示される被告ホームページに行き着いてしまう。そして図らずも被告ホームページの名誉毀損表現に触れてしまい、その表現行為による誤った情報を受領してしまうのである。
このように、インターネット上の言論は、それが名誉毀損表現である場合に、ひとたびそれがネット上に流通すると、原告についての情報群の一部として、原告についての情報を求めた人に容易に届くようになってしまうという特徴がある。
このような被害の大きさ、被害の拡大の容易さから、インターネット上での言論は、新聞・雑誌などの従来型のメディアによる表現に増して、他者の名誉を侵害することの無いよう、その表現にはより一層十分に意を用いなければならないものである。
また、ひとたび名誉毀損が行われてしまった場合には、その名誉を回復するためには、同じメディアでの謝罪のみでは足りない。当該記事を削除するだけでなく、検索にかかる表現での謝罪記事を掲載し、さらに他の媒体を用いての謝罪広告を行うなど、十分な被害回復の措置がとられなければ、その被害が回復することはないのである。
3 本件記事により摘示された事実
(1)名誉毀損の成否を判断するにあたっては、以下のような背景事情を考慮する必要がある。
(i)環境ホルモンのリスク認識をめぐっては、「環境ホルモン問題は大した問題ではない」という意見と、「人間や野生生物にとって看過できない重大な課題である」という意見まで、専門家の間でも大きく意見が対立していたが、特に、本件シンポジウムが開催され、また本件記事が書かれた2004年末当時は、環境省が姿勢を変更したこともあって、特にその対立が激化していた。なお、前者の意見は、産業界の研究者や、被告のような環境ホルモン研究の専門家ではない学者・ジャーナリストが主張していることが多く、原告をはじめ環境ホルモン研究者の多くは、後者の立場に立っていることは、原告準備書面(3)1(3)に述べたとおりである(甲22;原告陳述書(2)4項11頁〜、乙11被告陳述書4項)。
(ii)被告の本件ホームページの主たる読者は、研究者、技術者、ジャーナリスト、行政官、政治家、学生、院生であり(乙11:被告陳述書9項)、環境科学の専門家、及び環境科学以外の専門家が主であり、市民団体の指導者も読者となっている(被告本人尋問調書5頁)。
すなわち、多くの読者は、(i)記載の環境ホルモンのリスク認識をめぐる意見対立の状況を把握している人びとである。したがって、本件摘示事実や名誉毀損の成否を判断するにあたっては、このような読者が、背景事情についての知識をもって、本件記事を読むということを勘案する必要がある。
(2)また、名誉毀損の成否については、上記の背景事情に加えて、本件記事の本文はもとより、見出し、リード記事を総合して判断する必要がある。したがって、本件で問題となっている被告のホームページ上の本件記事(甲1)の問題部分「最初の情報発信に気をつけよう」という小見出しの記載の意味は、 「雑感286−2004.12.24」の記事全体の中で、その最後の部分として通常どう読まれるかという目で見ることが必要である。以下、本件記事の構造の中での問題部分の意味を検討する。
(i)全部で5項目からなる本件記事は、題名が「環境省のシンポジウムを終わって一リスクコミュニケーションにおける研究者の役割と責任(下線は原告代理人・以下同じ)」である。
最初の第1項で「常に、最初の情報は学者から出しているので、学者は最も責任のある立場にあるとも言える。それを自覚して欲しいし、わが国の環境ホルモン騒動でも学者の責任は大きい。」と記載して、本件で問題となっている最終項(第5項)「最初の情報発信に気をつけよう」に繋げるための問題提起を行っている。
第2項で影響の大きさについての情報発信における学者の責任について、第3、第4項では、環境ホルモン問題のリスクコミュニケーションの失敗と学者(研究者〉の責任を論じている。
本件で問題となっている最終項(第5項)では、ふたたび被告が第1項に記載した上記の問題提起を受ける形で「最初の情報発信に気をつけよう」と題している。そして本文冒頭に第1から第4項め記載を集約して「環境ホルモン問題では、最初に出された情報が皆の頭の中に染みつくと、そこから抜け出すことが如何に難しいかを教えてくれる。そして、この最初の情報は、学者が出し、学者が増幅していることに注意を喚起したい。今後は、ここに気をつけよう。」と記載した上で、次の行から、「パネリストの一人として参加していた、京都大学工学系研究科教授の松井三郎さんが、新聞記事のスライドを見せて、『つぎはナノです』と言ったのには驚いた。要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。」という本件で問題となっている記載に入っている。
(ii)このように、本件記事は、環境ホルモン騒動に責任のある学者一般への批判という形をとりながら、最後には原告への非難に集約するように構成されており、全体がそのために書かれているというような構造になっているのである。
これについては、本件ホームページの読者が、次のような、誠に正鵠を得た意見を寄せている。「論文などの技術レポートのみを扱っている人は感じないと思いますが、文学作品として読むと、雑感286全てが松井先生の悪口を言うために考えられた構造のようにみえます。それまでの別の批判を全て受ける形で、最後に松井先生への批判となっているので、それまでの別の批判は松井先生の悪口を増幅したいための前ふりと読むことが可能のようです。」 (乙9−46)。
(3)本件記事における摘示事実
上記のような環境ホルモン問題をめぐる意見の対立状況の存在と原告及び被告の立場を前提に、本件記事の全体の構造と、題名・見出し・本文の各記載を、普通の注意と読み方とを基準として本件記事の5項の記載を読むと、これにより摘示されているのは、次の2つの事実であるというべきである(原告準備書面(4)1)。
(i)訴状第2請求の原因2項(1)1)記載の記事(以下、「本件記事1)部分」という)の摘示事実
環境ホルモン研究を推進し、そのリスクを主張してきた研究者であり、環境ホルモンのリスクコミュニケーションの失敗に責任のある学者の一人、である原告が、本件国際シンポジウムにおいて、「環境ホルモン問題は終わった、今後社会が関心をもつべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子の有害性である」との趣旨で、新聞記事のスライドを見せて「つぎはナノです」と発言したこと。
(ii)同2)記載の記事(以下、「本件記事2)部分」という)の摘示事実
原告は、本件国際シンポジウムにおいて、新聞記事のスライドを見せてナノ粒子の有害性について問題提起したが、その問題提起の仕方は、原論文も読まずに又は十分に吟味することなく、ただ新聞記事に書かれていることをそのまま主張するという、およそ専門家にあるまじき、いかにもお粗末なものであったこと。
(4)本件記事1)部分の摘示事実について
(i)「パネリストの一人として参加していた、京都大学工学系研究科教授の松井三郎さんが、新聞記事のスライドを見せて、『つぎはナノです』と言ったのには驚いた。要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。」という記事を普通に読めば、被告は、(原告が)「『つぎはナノです』と言ったのには驚いた」と書いていることから、原告が「環境ホルモンは終わった。今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう」という意味のことを言ったから驚いたのである、と読める。このことは、引き続き、(つぎはナノですとは)「要するに・・・・という意味である」として、原告の発言の内容を要約して記載していることからも明らかである。
これに対して、被告は、この部分はプレゼンテーションの仕方を問題にしただけであるとか、「『驚いた』というのは、『次はナノです』として研究テーマを動かしたことに驚いたのではなく、『新聞記事のスライドを見せるだけ』というリスクコミュニケーション問題のイロハも理解しないやり方で、新しいナノ問題を取り上げたこと、しかもそれがリスクコミュニケーションのあり方を論じているシンポジウムの場であったことに驚いたのである」(被告準備書面3、4項)などと主張するが、後付けの詭弁に過ぎない。
(ii)「要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である。」との記載は、被告の意見・論評ではない。「原告が、要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味の発言をした」という事実の記載である。
そして、「環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう」の記載を普通に読むと、「原告が、『環境ホルモン研究の時代は終わった。私は今度はナノ粒子の有害性を問題にしようと考えている』という意味の発言をした。」という事実があったという記載であることは明らかである。
この部分の記載が、上記のように読まれることは、被告ホームページの読者から寄せられた本件記事を読んでの感想・意見の中に、1)部分について、次のような感想・意見があることからもわかる。
・「松井さん、次の研究費獲得の準備か。なかなかさかしいな」(乙8−2、4行目)
・「松井氏の発表は、私には次のように聞こえます。『ダイオキシンヘの不安により、研究費が増えるなどして、ダイオキシンを口実にした研究を行うことができた。最近は研究費が減額されている。次はナノである。ナノに対する不安を強調して、ナノを口実にした研究をしよう。』」。(乙8−49(2)、2行目)
(iii)これに対し被告は、この記載について、「被告として、原告の発言の趣旨を『社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である』というものと受け止めたということである。(中略)これは被告の解釈を示すものであることは明瞭である。」(被告準備書面2、4(1))などと主張して、本件記事の意味をことさらに言い替えようとしている。
さらに被告は、「環境ホルモンは一段落した、つぎは、ナノ粒子の有害性が大きな問題になると言っていると私は受け止めました。」(乙11:被告陳述書11項)、「『終わった』と『一段落した』は表現の問題(にすぎない)というふうに思います」、「『ナノ粒子の有害性を問題にしよう』と『ナノ粒子の有害性が大きな問題になる』は同じだ」(被告本人尋問調書29〜30頁)として、さらに記載の意味をねじ曲げようとしている。
しかし、原告は「環境ホルモンは終わった」という発言は一切していないし、そのような趣旨の発言もしていないことは明らかである(乙5)。
おそらく、被告は、乙5のテープを聞いて、原告が「環境ホルモンは終わった」と言った事実がないことがわかったが、本件記事には原告が『環境ホルモンは終わった』という意味の発言をしたと書いてしまっているため、これに困って、「これは被告の『受け止め』『解釈』である」と主張したり(被告準備書面2、4(1))、「環境ホルモンは一段落した」と言い換えを行ったり、「社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である」とか「ナノ粒子の有害性が大きな問題になる」などというように、「原告」ではなく「社会が」問題とするであろうというような表現にすり替えようとしているのである。
しかしながら、「今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう」(甲1)というのは、「社会が」ではなく、原告の意思に基づいて、主体的にナノ粒子の有害性の問題提起をしていこうという意味であることは明らかであって、このような主張は被告の言い逃れにすぎない。
(iv)仮に、意見・論評にあたるとした場合、「次はナノです」という発言のみの前提事実から、「要するに環境ホルモンは終わった,今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である」との意見を推論していることになるが、このような論評には飛躍があり、事実と意見との間に合理的推論を欠き、公正な論評とはいえないことは明らかである(東地判平2.3.26判時1343・62、東地判平9.3.25判タ960・229など)。
(v)また、被告は、「環境ホルモンは終わった」という部分は主要部分ではないと主張している。しかしながら、本件記事は、環境ホルモンのリスクコミュニケーションの失敗と学者の責任について記載されているが、その前提には、「環境ホルモンのリスクは大したことはなかった」、つまり「環境ホルモンは終わった」という被告の考え方があり、原告はこのような考え方には異論があったのである。加えて、本件記事が書かれた当時は、学者などの間でも「環境ホルモンは終わった」派と「終わっていない」派との聞で意見対立が激化していたのは既述のとおりである。このような状況を勘案すると、原告が「環境ホルモンは終わった」と発言したという事実は、原告の社会的評価にかかわる重要な部分であることは明らかである。
(5)本件記事2)部分の摘示事実について
(i)本件記事2)部分の「こういう研究結果を伝える時に、この原論文の問題点に触れてほしい。学者が、他の人に伝える時、新聞の記事そのままではおかしい。新聞にこう書いてあるが、自分はこう思うとか、新聞の通りだと思うとか、そういう情報発信こそすべきではないか。情報の第一報は大きな影響を与える、専門家や学者は、その際、新聞やTVの記事ではなく、自分で読んで伝えてほしい。でなければ、専門家でない。」との記載を、普通に読むと、次の事実を読み取ることができる。
(ア)「こういう研究結果を伝える時に、この原論文の問題点に触れてほしい。」との記載から、「原告は、ナノ粒子の有害性についての研究結果を伝えたが、原論文の問題点に触れなかった」という事実
(イ)「新聞の記事そのままではおかしい。」との記載から、「原告の発表は新聞の記事そのままであった」と言う事実
(ウ)「新聞にこう書いてあるが、自分はこう思うとか、新聞の通りだと思うとか、そういう情報発信こそすべきではないか。」との記載から、「原告の発表には当該問題についての自己の見解に関する情報発信がなかった」という事実
(エ)「専門家や学者は、その際、新聞やTVの記事ではなく、自分で読んで伝えてほしい。」との記載から、「原告は(論文を)自分で読まずに新聞記事をそのまま発表した」という事実
(オ)「でなければ専門家でない。」との記載から、「原告は専門家でない」、ないしは「原告は専門家の名に値しない発表を行った」という事実
これは要するに、「原告は、本件国際シンポジウムにおいて、新聞記事のスライドを見せてナノ粒子の有害性について問題提起したが、その問題提起の仕方は、原論文も読まずに又は十分に吟味することなく、ただ新聞記事に書かれていることをそのまま主張するという、およそ専門家にあるまじき、いかにもお粗末なものであった』という事実の摘示にほかならない。
(ii)被告は、「センセーショナルな見出しのついた新聞記事を、何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて、問題があるような話をするなどということは、参加者に誤った印象を植え付ける危険性が高く、専門家としてのプレゼンテーションとしては適切ではない。(中略)被告は、そのようなプレゼンテーションは不適切であると批判したものである。」という趣旨で本件記事を書いたと主張している(答弁書第3、2〜3項)。
この主張は、まさに「原告が何ら専門家としての判断を加えずに、そのまま掲げて、問題があるような話をするなどということ(事実)」、すなわち上記(ア)から(エ)の事実があったことを前提として指摘して、そのうえで、(オ)の「原告はそのように専門家の名に値しないお粗末なプレゼンテーションを行ったという事実」を記載していることを認めたものである。
(iii)本件記事2)部分が、普通、このように読まれることは、被告ホームペ一ジの読者から寄せられた本件記事を読んでの2)部分に関する感想・意見の中に、次のような記載があることからもわかる。
・「自分の研究を有利に進めるため、扇情的な新聞を利用する態度を被告は批判しているのだと思います」(乙8−6、2項一番下)
(本件記事から、「原告が、自分の研究を有利に進めるため、扇情的な新聞を利用した」と受け止め、これを前提として意見を述べている)
・「あえて名誉毀損の箇所を探すと、あまりよろしくない発表の仕方の例示として松井先生の発表が挙げられているという印象を持たれることかもしれない」(乙8−10、下から7行目)
・「むしろプレゼンテーションが下手で発言の意図が分からない、論拠の出典がいい加減だ、とのことを暴露されたので(事実ですが)松井さんの権威や名誉が傷付き、今後の研究に支障が出る、との提訴ならまだ分かりますが」(乙8−28)
・「原告の新聞のみを用いた発表を専門的な論文等についての専門家としての発表のあり方の観点から批判したものであって、専門家として正当な批評行為である」(乙8−31、2項下から5行目)
(本件記事から「原告が、新聞のみを用いた発表をした」と受け止め、これを前提として意見を述べている)
・「原告は、原文にあたらず新聞記事の見出しを見ただけで事実確認をせず、それにも関わらず大学教授の肩書きのもとに公表し,『重大事である』と公表していると読みました」 (乙9−31、・第2パラグラフ)
・「ナノ粒子の問題について原著でなく、ローカルの新聞記事で問題提供をした松井教授は、『専門家や学者は、その際、新聞やTVの記事ではなく、自分で読んで伝えてほしい。でなけれぱ、専門家でない』との内容により、専門家でないと指摘されたと感じた」(乙9−42、理由2)
・「松井先生のプレゼンは、専門家とは言えない、あるいは、専門家の責任を放棄している、というようなプレゼンであったというような印象を受けました。」(乙9−66、13行目)
・「プレゼンあるいは情報発信ということへの取り組みについては、雑感を見ることによって、松井先生が、その問題点に措いては不得手な学者であるというマイナスの印象を持つことになりました。私の受けた印象では、このことを持って、雑感の記述によって、松井先生の社会的評価が低下したということは言えるように思いました。」(乙9−66、下から5行目)
なお、前記(4)(ii)に引用した感想・意見を含むこれらの感想・意見は、被告ホームページの読者が、被告の「今後言論や相互批判が制限されてしまうという危機感が強いと思います」(乙10、2枚目12行目)という誤った情報提供のもと(さらに詳しい情報を求める人のために「環境ホルモン濫訴事件=中西応援団」ほか、被告を応援するウェブサイトが紹介されている:乙10、3枚目最後部分)、被告の「力を貸して下さい」(乙10、1・2枚目)という求めに応じて、被告宛に寄せられたものである。すなわち被告に力を貸した人たちでさえも、本件記事を読んで、以上のように受け止めたのであることを付言する。
(iv)被告は、「自分で読んで伝えてほしい。でなければ専門家でない」という記載で問題にしているのは、「自分で読んで伝えること」であり、「読むこと自体」ではない、「読む」ことと「読んで伝える」ことでは全く意味が異なると主張している。しかしながら、この記載を素直に読めば、上記のとおり「原告が自分で論文を読まずに、新聞記事をそのまま発表した」という事実を読み取ることは明らかであって、被告の主張は詭弁としかいいようがない。
(6)本件記事1)2)部分の記載が原告の名誉を毀損したこと
(i)本件記事1)部分の記載は、環境ホルモン研究に真摯に取り組み、環境ホルモン学会副会長、文部科学省特定領域研究班『内分泌撹乱化学物質の環境リスク』の代表を務め、さらに環境ホルモン研究を進め発展させていこうとしている原告について、本件記事の読者に、「原告は、環境ホルモン研究を推進し、そのリスクを主張し、環境ホルモン問題があたかも大変な問題であるかのような情報発信をし、また増幅してきた研究者の一人であって、環境ホルモンのリスクコミュニケーションの失敗に責任のある学者であるにもかかわらず、手のひらを返したように環境ホルモン研究に見切りをつけ、『(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である』という趣旨の発言をして、環境ホルモン騒動の責任をとらないままに、新たな危険情報の発信をしている。」、「原告が、環境省主催の国際シンポジウムという公の場において、研究者に共通する重要なことがらについて、高名な学者である被告も見逃せないような節操の無い発言をした」、「原告は研究費がつく間だけ他人を利用して、研究費がつかなくなると、さっさと次の時流のテーマに移ってしまうような学者である」などという、誤った、非常に悪い印象を与え、原告の研究者としての名誉を著しく傷つけたものである。
(ii)被告は、「環境ホルモンは終わった」という記載によって原告の社会的評価が下がるわけではないと主張する。しかしながら、既述のような背景事情の下で、原告が、こともあろうに「環境ホルモンは終わった」派に転じたかのように表現されると、文科省の特定領域研究班のリーダーを務め、環境ホルモン学会の副会長の地位にある学者としての原告の社会的評価は著しく低下することは明らかである。このことは、同じく研究者である有薗幸司氏の陳述書(甲23〉を読めばよくわかる。また、既述のとおり、被告の支援者の人々の中にも、
・「松井さん、次の研究費獲得の準備か。なかなかさかしいな」(乙8−2、4行目)
・「松井氏の発表は、私には次のように聞こえます。『ダイオキシンヘの不安により、研究費が増えるなどして、ダイオキシンを口実にした研究を行うことができた。最近は研究費が減額されている。次はナノである。ナノに対する不安を強調して、ナノを口実にした研究をしよう。』」。(乙8−49(2)2行目)
というような感想・意見が述べられていることからも明らかである。
(iii)また、本件記事2)部分の記載は、「原告は、環境省主催の国際シンポジウムという公の場において、論文を紹介してナノ粒子の有害性について問題提起を行ったが、その際、何新聞の記事なのか、また見出しもよく分からないような新聞記事を、原論文の問題点に何ら触れることなくそのまま使って、専門家としてするべき情報発信をすることなく、唐突でお粗末なプレゼンテーションを行った。原告は、研究者のイロハであるプレゼンテーションの仕方も知らない学者であり、専門家の名に値しない。」との誤った印象を与え、原告の研究者としての名誉を著しく傷つけた。
原著・原論文にあたること、プレゼンテーションの仕方は、研究者の基本的作法・技術であり、イロハであるが、これができていないという誤った指摘は、原告の研究者としての基礎的素養を強く疑わせるものである。
このことは、被告ホームページの読者から寄せられた本件記事を読んでの感想・意見の中に、次のような記載があることからもわかる。「私も仕事や自らのフィールドワークとしている分野において、必要と思われる論文や行政文書等については、それらの解説や評論のみでなく、入手可能な限り原著論文を探して読み、自分自身で考察する作業を実施します。こうした手法は、私は大学生時代に指導教官や先輩から学んだもので、ごく基本的手法だと理解しています。」(乙9−4・下から9行目)。
(iv)原告は、本件記事を読んだ複数の研究者から、原告を心配しての問い合わせを受けた。ごく親しい人たちは「記事の内容は本当か?」、「先生は環境ホルモン研究を放棄されたのですか?」、「中西氏から貶められているぞ」、「ずいぶん酷いことが書いてあるよ」、「名誉毀損でいじめられてるね」、「あのまま放置していいんですか」との質問や指摘をされてきた。原告が副会長を務める環境ホルモン学会でも同様の質問を受けた。(甲9:原告陳述書5(1)、甲22:原告陳述書(2)8(3)23頁、原告本人尋問調書51〜52頁)。
直接面識のない人は何も言っては来ないが、本件記事を読んで、原告を「いい加減な学者」と誤解しているものと思われる。原告は文部科学省科学研究補助金特定領域研究(1)「内分泌撹乱物質の環境リスク」の公募研究リーダーを努めたが、この研究に加わった人たちが、本件記事の内容を信じたら、「松井氏は何という人だ。9億円もらって自分たちを利用しただけなのか!時流に乗って金がつく間だけやり、金がつかなくなったらすぐ次の問題に移ってしまう人なのか!」、「松井氏が原論文も読まず、新聞報道だけで問題提起するような底の浅い人なのか!」と思い、原告に対する信頼感、尊敬の念を失い、自分たちの研究に対する熱意さえ失うことになりかねない。また、原告が「環境ホルモン空騒ぎ派に鞍替えした」などと思われたら、若い研究者に対し何も発言できなくなってしまうのである(甲23:有薗陳述書63)5))。
このようなことからも、原告が本件記事1)2)の部分の記載によって、その名誉を著しく傷つけられたことは明らかである。
4 摘示事実は真実ではないこと
前記の各摘示事実は、以下のとおり、主要な部分について真実ではない。
(1)本件記事1)部分の摘示事実の真実性について
(i)本件記事1)部分が摘示している「(ア)環境ホルモン研究を推進し、そのリスクを主張してきた研究者であり、/(イ)環境ホルモンのリスクコミュニケーションの失敗に責任のある学者の一人である原告が、/(ウ)本件国際シンポジウムにおいて、/(エ)『環境ホルモン問題は終わった、今後社会が関心をもつべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子の有害性である』との趣旨で、/(オ)新聞記事のスライドを見せて/(カ)『つぎはナノです』と発言したこと。」との事実のうち、真実なのは、(ア)(原告が)環境ホルモン研究を推進し、そのリスクを主張してきた研究者であること、(ウ)及び(オ)本件国際シンポジウムにおいて、新聞記事のスライドを見せたことのみである。
(ii)(エ)「『環境ホルモン問題は終わった、今後社会が関心をもつべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子の有害性である』との趣旨で、(カ)『つぎはナノです』と発言したこと。」は真実に反する。
まず、原告が、「環境ホルモンは終わった」とか、「今後社会が関心をもつべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子の有害性である」と言った事実はないことは、本件シンポジウムの反訳から明らかである(乙5−2:反訳書12〜15頁、21〜22頁)。
また、次の通り、そのような趣旨の発言もしていないことも明らかである(原告本人尋問調書13頁〜)。
すなわち、原告は、本件シンポジウムにおいて、インディゴ、インディルビンの発見から(甲8:プレゼン用スライド第6図〜第8図)、環境ホルモンの1種であるダイオキシンの毒性メカニズムに関する仮説を紹介し(甲8:プレゼン用スライド第9図〜第12図)、このダイオキシンの毒性メカニズムに関する研究成果を、ナノ粒子への対策に予防的に適用できるのではないかという趣旨で新聞記事を示し(甲8:プレゼン用スライド第13図、甲22:原告陳述書(2)20頁)、 「我々は予防的にどうやって次の問題に繋げるのか、今回学んだ環境ホルモンの研究はどうやって生かせるのか。私は次のチャレンジはこのナノ粒子だと思っています。」と発言したのである(乙5−2:反訳書15頁)。
原告は、環境ホルモン研究の進展を説明する中で、「人工的な化学物質の問題を研究してきたはずだったのに、難易性(内因性の誤記)unknownがいっぱいあるということがわかってきたわけです。このように環境ホルモンの研究というのは、人工的化学物質の問題を提起しながら、実は、いままでわかっていなかった生命の秘密が同時に理解されてきています。」(乙5−2:反訳書14頁下から5行目)、「ダイオキシンというのは、・・・・こういう全くわけのわからないものが発見されたのです。まだまだ我々は生命秘密がわかってないのです。」(乙5−2:反訳書15頁1行目)などのように、環境ホルモン研究が「わかってきた」「生命の秘密が同時に理解されてきています」「まだまだ我々は生命の秘密がわかってないのです。」という段階であって現在進行形であること、ようやく緒について、これからの学問であることを前提に話をしていたのである。
そして、これまでの環境ホルモン研究(この場合、ダイオキシンの解毒機構研究)の成果を、今まさに開発が進められつつあるナノ粒子についても類推適用して、予防的に対策を取るために生かすことができるのではないか(甲22:原告陳述書(2)20頁)と発言し、被告は環境ホルモン問題は空騒ぎだったと言い、それに同調するパネリストもいるが、原告としては、環境ホルモン問題について積み上げられてきた地道な研究は決して無駄ではなく、今後もさらに発展させていくべきであるということを説明したものである。
(iii)(イ)について、「リスクコミュニケーションが失敗であった」というのは被告の独善的な決めつけであって、環境ホルモンの危険性について憂慮し研究をしてきた学者たちは、科学者の責任として、結果として無害であるかもしれなくとも、有害なものを間違って無害とすることによって取り返しのつかない事態を招くことよりは人類にとって望ましいという予防原則の考え方にたって活動してきたものである(甲8:プレゼン用スライド第16図、甲22:原告陳述書(2)21頁、乙5−2:反訳書22頁)。何事においてもそうであるが、環境ホルモン問題についても振り返ってみて改善すべき点はあるであろうし、それがなければ進歩も望めないが、環境ホルモン問題について、世界的に多くの研究成果が積み上げられ、ヒトと生態系への影響が懸念されていること、さらなる研究が進められていること、WHOでも国際的優先事項であるとされていることからみて、「リスクコミュニケーションの失敗」であったとの評価で一致している訳ではなく、真実ではない。
(2)本件記事2)部分の摘示事実の真実性について
(i)「原告は、本件国際シンポジウムにおいて、/(ア)新聞記事のスライドを見せて、/(イ)ナノ粒子の有害性について問題提起したが、/(ウ)その問題提起の仕方は、原論文も読まずに又は十分に吟味することなく、ただ新聞記事に書かれていることをそのまま主張するという、およそ専門家にあるまじき、いかにもお粗末なものであったこと。」との事実のうち、真実なのは、(ア)原告が新聞記事のスライドを見せたということだけである。
(ii)原告が新聞記事のスライドを見せたのは、上記(1)で述べたように、「(環境ホルモンである)ダイオキシンの毒性メカニズムについての研究成果を、今まさに開発が進められつつあるナノ粒子についても類推適用して、予防的に対策を取る必要があるのではないか」(甲22:原告陳述書(2)20頁)という発表に際し、当時ナノ粒子の問題がクローズアップされてきていた状況を示したにすぎず、(イ)「ナノ粒子の有害性について問題提起した」という事実はない。
(iii)(ウ)について、原告は、原論文を読んで内容の検討を行っていた(原告本人尋問調書15頁)。
そして、原告は、前述のように、新聞記事(甲8:スライド第13図)を、ナノ粒子の有害性の問題提起をするために使ったわけではなく、その新聞記事の内容を説明したのでもない。新聞記事の見出しは、「ナノ粒子脳に蓄積」「米、毒性評価を研究へ」というものであり、記事の内容は「ナノ粒子が脳などに蓄積して健康に悪影響を及ぼす可能性があるとして、米政府が毒性評価の本格研究を始める」というものであるが、原告は、ナノ粒子が脳などに蓄積する等と言うことは一切言っていないし、アメリカ政府が毒性評価を始めるなどにも一切言及していない。このように、原告が、「ただ新聞記事に書かれていることをそのまま主張」したということも全くなく、被告の本件記事が摘示する事実は真実に反する。
以上のように、被告ホームページ上の問題部分の摘示事実は、その重要な部分において、真実に反する。
5 真実性法理における相当性、公共性、公益性について
事実を摘示しての名誉毀損の場合、被告が免責されるためには、前述の真実性のほか、1)表現が公共の利害に関すること、2)専ら公益を図る目的でなされたこと、3)真実と信ずるについて相当の理由があることが証明されなければならないとするのが判例・通説である(最判昭41.6.23判時453・29、最判昭58.10.20判時1112・44など)。
被告は、この点について明示的に主張していないが、本件においては、少なくとも2)公益性、及び3)相当性を欠くものであることを念のため指摘しておく。
(1)公益性について
最高裁は、公益目的の有無の認定に関しては、摘示する際の表現方法や事実調査の程度などが考慮されるべきであると判示している(最判昭56.4.16判時1000・25「月刊ペン事件」)。近時の裁判例の中にも、公益目的の判断方法について、発言の動機等の主観的関係のみならず、発言の状況、事実摘示の際の表現方法の相当性、根拠資料の有無等の客観的関係も考慮すべしとし、結論として公益目的を否定したものがある(東地判平2.1.30判タ730・140)。
本件においては、本件記事の発言は、本来なら本シンポジウムの場で行うか、そうでないとしても直接に原告宛に行うか、少なくとも反論の機会の保障のあるメディアで行うべきものであって、いずれの方法にもよることなく、わざわざ原告が反論できない被告個人のホームページというメディアを用いて、しかも事前の事実確認もなされないまま掲載されたものであって、前述の裁判例に照らすと問題があると言わざるを得ない。
また、表現の仕方も、本件シンポジウムにおける、原告の発表内容のごく一部だけを取り上げ、いかにも全体のプレゼンテーションの仕方がお粗末であるかの印象を与えるような記載で、いかにも「揚げ足取り」と言わざるを得ないものである。このような事情を勘案するならば、本件記事の掲載は、専ら公益を図る目的でなされたものとは認められないことは明らかである。
(2)相当性について
被告は、事前に原告に対して何らの確認もせず、独善的に本件記事を記載したものであって、到底真実と信じるにつき相当の事由があったものとはいえないことは明らかである。
被告は、第13図についての原告の当日の発言が分かりにくいものであったことを強調しているが、もしそうなら、なぜ、本セッションの場で確認しなかったのか。特に・被告が摘示した原告の発言や態度は、被告が座長を務める本セッションのテーマそのものに直接かかわる重大なものであったのであるから、なおさら本セッションの場で問題提起するのがセッションの目的にも適うことだったはずである。もし仮にセッションで確認できなかったとしたら、セッション終了後でも、直接原告に事実確認する機会はいくらでもあったはずである。ましてや、被告は、本シンポジウムでの原告の発表内容についてよく理解できていなかったと供述している(被告本人尋問調書28頁20〜21行目)のである。もし、分かっていないところがあったり、誤解しているかも知れないと、思うのであれば、後からでも、断定的な本件記事を掲載する前に、原告本人に質問ないし確認すべきである。被告は、そのような事前の確認もせず、自己の独善的な思い込みに基づいて、真実でないことを記載しているのである。このような事情を勘案するならば、本件は到底相当性が認められる事案ではないことは明らかである。
6 学問的批判ではないこと
被告は「学問的批判」をもって違法性阻却事由としての正当業務行為(例えば、議員の議会での発言、弁護士の弁論活動など)であると主張しているが、一般的に「学問的批判」であることをもって、何らの限定なく正当業務行為として違法性を阻却することを認めることは、学者に対してあまりにも免責特権を与えるもので、到底認められるものではない。
言うまでもないが、正当業務行為として免責の対象となるのは、弁護士の弁論活動や議員の議会での発言に限られるのであって、弁護士や議員が個人のホームページ上でなした言論にまで、そのような免責特権が受けられるわけではない。また、議員の議会における発言であっても、真実性の立証がない以上、名誉毀損の成立を認める例が多数なのである。
本件においては、「学問」といっても、被告個人のホームページ上という、反論の余地のない一方的なメディアによる独善的表現であって、そもそも「学問的批判」にさえ該当せず、したがって、到底正当業務行為としての免責が認められるような場面ではないことは明らかである。
学問的批判というなら、原告の発表内容を正しく理解したうえで、その発表内容を学問的裏付けをもって批判するのでなければならず、また、研究発表の仕方についての学術的見地からの批判は、発表者の発表内容を正しく把握したうえで、発表の仕方がそのような内容を発表するための方法として適切でない場合に、はじめて成り立っものである(原告準備書面(4)2(2))。
しかし、被告の本件記事は、原告が「つぎはナノです」、「環境ホルモンは終わった。今度はナノ粒子の有害性を問題にしよう。」などと言っていないのに、そう言ったと決めつけて、それを非難するものであって、原告の学問的見解を正しくとらえて、それに対して、学問的見地から批判するというものでは全くない。
また、被告は、原告がしたプレゼンテーションの趣旨を不注意にも誤解したうえ、原告が用いた新聞記事を見逃し、後にそれを確かめることもせずに、原告の発表方法が、被告が誤解した趣旨の発表としては不適切である、原告が原論文を読まずに新聞記事そのままを伝えたなどと、真実に反する事実をあげて、一方的な非難をしているにすぎないから、これもまた、学問的批判にはあたらない。
よって、この点に関する被告の主張は、主張自体失当であるというべきである。
7 損害とその回復措置
以上のように、原告は、被告の本件記事によって、その研究者としての名誉を著しく侵害された。損害および、その回復に必要な措置については、訴状第2、3項、4項に記載の通りである。
なお、本件シンポジウムの開催に、日本内分泌攪乱化学物質学会(通称:環境ホルモン学会)が協力していたこと(乙4:プログラム・アブストラクト集、表紙)、本件シンポジウムと環境ホルモン学会は時を同じくし、同じ場所で学会発表を行っていたことから、本件シンポジウムには同学会の会員も多く参加していた。また被告のホームページを読んでいる会員も多数ある。
通常シンポジウムは、パネリスト各自の発表時間も限られているので、たとえ図表を使って発表するとはいえ、十分意を尽くしきれない傾向がある。そのようなシンポジウムのコーディネーターであった被告が、本件のような記事を自己のホームページに記載して原告を誹謗中傷したのである。しかも被告は訴訟係属後も自らのホームページで原告の提訴そのものを批判し続けている。しかもその中には被告の思い込みや、悪意による誤解に基づく誤った情報も含まれているので、原告の名誉を回復するためには、環境ホルモン学会機関紙への謝罪広告掲載が不可欠である。
8 提訴後の被告の態度について
原告の準備書面(2)で詳述したように、被告は、本件提訴後もずっと自らのホームページにおいて、原告や原告代理人らを侮辱したり、その名誉を侵害する言論を繰り返している。そのやり方は、本件名誉毀損行為と同様に、虚偽の前提事実を作り上げて、それを基に他者を名指しで批判するというもので、このような態度を見る限り、被告は、全く自己の表現行為の問題性を理解できておらず、したがって全く反省できていないと言わざるを得ないのである。それどころか、本件裁判での主張を見ると、このような極めて問題のある名指し批判であっても、学問的なことに関わるものであれば、何を記載しても許されると考えているようである。被告本人尋問でも、被告には自己のホームページヘの記事の記載について、他者の名誉を毀損することのないように細心の注意を払うという、慎重かつ自己抑制的な姿勢など、微塵も感じられなかった。
しかし、もし、そうであるとすれば、被告は、今後も、「学問的批判」の名の下に、自分で勝手に作り上げた虚偽の前提事実に基づいて、他者への名指しの批判を続け、多くの者の名誉が傷つけられることにもなりかねない。ましてや、被告は高名な学者であり、社会的にも高い地位に就いているのである。このような被告の記事を真実であると誤信するものも少なくないと思われる。被告のような立場の者が、IT社会における節度ある書論を弁えていないならば、冒頭に述べたIT社会の影はますます肥大化していくに違いない。そして、それにより、学問に携わる者が自己の発言を歪曲され、名指しで批判されるのを恐れて自由闊達な意見が言えなくなり、かえって学問の発展が阻害されてしまうことを、原告は深く憂慮し