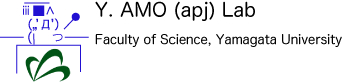|
|
- Info
第5回
- トンネル中の照明はなぜ発光ダイオードとかではないのですか?信号機とか電灯にどんどん採用されていますしナトリウムランプより電力削減できると思いますが。
→私に訊かれても……道路公団あたりに問い合わせてみてください。
- トンネルの中のオレンジ色の照明はナトリウムランプの光ということでしたが、なぜナトリウムランプが使用されているのですか。
→蛍光灯よりもコスト面で安いことと、見やすいことが理由だったかと……。道路公団のサイトを探してみてください。
- 電子の存在確率(電子雲)の話がありましたが、電子の位置は測定できないのでしょうか?現実で暮らしている実感との相違があって中々理解が難しかったです。
→構造解析の論文で、電子雲の密度を等高線で描いたものを見たことがあるので、やなり存在確率(密度)で観測されているようです。
- 今回の講義でもそうですが、放射能の話題が出るとほぼ確実に福島原発にふれますね。テレビでは外から帰ってきたら風をはたけばいくらかおちるとかないとか言ってますが、これから夏になり肌の露出が多くなります。肌についた放射能はどうなるんですか。
→放射能といっても、他の物質と何も変わりません。今問題になっているのはセシウムですが、土にくっついてあまり動かないようなので、外から帰ったら、埃を落とすとか洗うとかすれば済みます。ただ、今のところ、山形では、放射線の心配をするよりは紫外線の心配をするほうが現実的ではないかと。
- 今回もとても興味深い内容でした。ところでレーザーポインターなどは直接目に向けると目に悪いと聞きましたが、ライブなどの演出で使われているレーザなど同じ目に悪いのでしょうか。
→悪いです。出力によっては失明することもあります。
- 赤外線に当たると暖かいと言う事は、普通の光が暖かいのは含まれる赤外線によるものなのでしょうか。また、赤か緑のみの波長の光に当たっても温度は何も変わらないのでしょうか。
→可視光もエネルギーを運びますが、主に赤外線によるものです。どの波長でもパワーが大きければ最後は熱に変わります。ただ、普段生活している条件では、暖かさを感じるのは主に赤外線によるものです。
- メガネのレンズに光が当たると緑色のような色になりますが、どうして緑色なのでしょうか?暑さや度数によって別の色にならないのでしょうか?
→レンズ表面の薄いコーティングが原因かもしれませんが、測って確かめたわけではないのでちょっと自信がないです。銀行や郵便局に置いてある老眼用の眼鏡ではどうでしょう?凹レンズと凸レンズで同じに見えるようなら、度数の問題ではないことが確認できますので試してみてください。
- 血液型性格診断はうそということですが、人には血液型により差異はないのでしょうか。
→差異があるから輸血の時に検査しているわけで……。
- 身体に電気を流して痛みをなくすという商売はいかにもウソっぽいのですが、どうなのでしょうか。祖父が一回無料でやった時は本当に楽になったと言っていました。
→体に対する効果は、試験をしないと何とも言えない。臨床試験の結果があればとりあえず信用するか、といったところ。
- ケータイのカメラでリモコンなどの赤外線を写すと光って見えます。普段可視光線でないために見えない光をケータイでは見えるのはなぜでしょうか。
→ケータイのカメラのセンサー(たぶんCCD)が、赤外線にも感度を持っているから。世の中には、赤外線ビュアーといったものもある(真っ暗でも赤外線だけ画像にして見える装置)。
- うろ覚えで申し訳ないのですが、以前に野球ボールを富士算に何発もぶつけると、1球だけ富士山を通り抜けるといったたとえ話を物質波の話の時に聞きました。どういうことなのでしょうか。
→電子が移動できないような壁(ポテンシャル障壁)があっても、電子の波動関数は壁の向う側にしみ出すので、電子の存在確率が0ではなくなるという話。トンネル効果、で調べてみてください。富士山の話はたとえ話で、野球のボールになると、宇宙の寿命くらいの間ずっとぶつけていても通り抜けることはないかと。
- シュレーディンガーの波動方程式についてはまともに扱いはしないと思いますが、一次元空間でやると波動関数ψ(x, t)はイメージできる感じがするんですが、3次元空間での波動関数って、それを見て具体的に電子の挙動をイメージできるものじゃなくて、存在確率|ψ|2の方が大事なんだなあという認識で良いのでしょうか。かいつまんであったとはいえ、専門の量子化学っぽい授業よりずっとわかりやすかった。量子系のトピックがもうちょい続いてくれるとうれしい!!
→【わかる人だけわかればいい回答】ψそのものには物理的意味はなくて、物理的意味があるのはψの二乗の方です。あと、固有値として出てくるエネルギー準位と。で、ψとψの共役で演算子をはさんで積分したものが、観測される物理量の期待値で、実験結果と比較可能なものになります。結局、実験と比べてちゃんと合っててナンボの話なんで。
- 先生が考える、一般の人が一番だまされそうな嘘情報は何か?
→今だと、放射能騒動があるので、「○○で放射能が分解できる!除去できる!」系の話は、ひかかりやすい背景ができあがっているかと。
- 原子から光が出てくるときに、エネルギーの違う軌道から軌道へ電子が移るとあります。電子がどの軌道にあるかはそれぞれの原子で決まっていると習った気がしたので、理解できませんでした。軌道から軌道へ電子が移るとはどういうことか教えて欲しいです。
→波動方程式を解くと、電子の数よりもずっと多くのn,l,m,の組み合わせが出てきます。何もしなければ、軌道のうちエネルギーの一番低いところから電子が詰まっていって、エネルギーの高いところは空いています。これを基底状態といいます。大きな熱エネルギーや光のエネルギーを電子に与えると電子はエネルギーをもらって、エネルギーの高い(つまり元のnlmとは違う値をとる)軌道に移ります。これを励起状態といいます。励起状態は不安定なので、電子はエネルギーを出して基底状態に戻ろうとします。このとき、励起状態と基底状態のエネルギー差に相当するhνの光を出して戻ります。
- 波動関数ψの2乗がなぜ存在確率になるのですか?
→ちょっと簡単な説明は思いつきません。たとえば、「量子論の基礎」清水明著、サイエンス社、という本がありまして、120ページくらい読むと理由がわかります。
- 紫外線の方が強いエネルギーを持っているのなら紫外線の方がより熱を感じそうですが、なぜ「熱い」と感じることなく日焼けするのでしょうか。今日は電磁波の話が含まれていたが、昔、パナウェーブ研究所(?)があったことを思い出しました。宗教団体だったと思いますが、あれもエセ科学的なものだと思います。
→何にエネルギーを与えるかで違いが出ます。化学結合を切る方に主に使われるということでしょう。パナウェーブは宗教というよりはカルトです。科学を利用する宗教団体にまともなものはない、と思った方がいいです。
- 物理を習っていなかったのでおもしろかった。すべての原子に色(光)があることに驚いた。特定の金属のみに色があると思っていた。水素原子から出る光はどうやって見ることができますか。
→水素原子を閉じ込めて加熱すると見えるはず。
- 太陽光をプリズムに通すと7色に別れるというところがもう少しくわしく知りたい。
→http://www.ngk.co.jp/site/no162/content.htm に動画付きで実験の様子が出ています。波長によって屈折率が違うことを利用しています。
- 黒体輻射の部分があまりよく理解できなかったが、最後のインチキを見抜く話で、今日の話の大まかな所がわかった気がする。
- 物理が苦手だったので、難しく感じました。でも、「インチキを見抜くために」がおもしろかったです。
- とても興がわく話だった。
- この授業を受けてから「インチキ」を探るようになった。見抜きたいと思う。
- インチキ話は身の回りにたくさんあるんだな、と感じました。そうゆう話にだまされない人にならなくてはいけないと思います。
- 電子がぼんやりした存在だとは思わなかった。軌道がきちんと決まっていて、まさか、x、y、z軸に刺さったお団子のようなものだったとは。電子を身近に感じました。
- 科学に関するインチキは聞きたくもないし、自分でも言いたくないと思った。正しい知識を身につけていきたい。
- 波動水の話を聞くと、何でそんなのにひっかかるのかと思うが、心のノートについて自分になんの記憶もないことを考えると、油断するとすぐだまされるんだろうと思う。
- 波動って今いち自分にとって難しいイメージがあるから波動関連のウソを言われても信じてしまうなと思った。
- インチキ話を聞いて、自分でちゃんと調べて物は買おうと思いました。
- 物理系の話で難しかった。
- 物質を見るのに波長が関係するとは知らなかった。だから可視光線というのかと思った。
- 世の中はウソやキレイ事ばかりだと思った。誤った情報にだまされない力をこの授業でつけていこうと思う。
- 「波動」の話、おもしろかったです。
- 量子力学の内容がとてもためになった。
- 毎回、インチキ科学(化学)を聞けてためになる。
- 難しい内容で理解するのが大変だった。
- 最後の波動系インチキの話はおもしろかったです。エセ科学と言えるかわかりませんが、最近、DHMO(水酸)?なるものの話を聞きました。
→DHMOは、ただの水です。
- 印刷がうすいのはどうにかなりませんか?図がよく見えなくて残念です。
- 最後のツッコミが面白かったです。
- さすがに「人と気が合う時、同じ波動を出している」は嘘だとわかるが、「波動水」など少し科学風に言われてしまうと、だまされてしまいそうな気がした。電子の軌道のところが難しかった。
- 赤外線と紫外線でそんなに違うものだと知らなかった。紫外線は暖かく感じないのには驚いた。
- 波動性=確率の波、ということを初めて知った。
- 来週の基礎化学Iで中間テストに来る範囲だったので講義を受けることができてよかったです。プリントの図が薄いことが気になります。
- 数字の桁が1つ違うだけでもすごく違うものなんだなと思った。
- 農学部では専門として電子の軌道の話はやらないが、興味があるからもっと電子軌道や専門の話を聞きたい。プリントがはっきり見えないのが残念だ。このプリントではうまくイメージがわかない。嘘の主張に基づく「波動」系のインチキ装置。そのようなものがあるのは驚きだ。違反の科学的今kひょのない都合の良い話の装置が販売されているのは恐い。ちゃんと知識を増やしてそのような誤った装置には手を出さないように気を付けたい。
- 最後の話が面白かった。ある程度の科学的知識が必要なのだと感じた。
- 世間にひそんでいる「ウソ」が多いことに驚いた。光の話はわかったが後はむずかしかった。
- 難しくてよくわからなかった。
- 難しかったです。
- 今日の授業もわかりやすくて楽しかったです。
- 電子の軌道の話は高校の化学の時間で学習する機会がありました。しかし当時はセンター試験の学習で必死だったので聞き流していましたが、今になってしっかりと聞いておくべきだったと思います。
- 基礎的な科学を身につけて、波動系インチキにひっかからないようにしたい。
- 専門の授業できいた波動の話よりずっと分かりやすいと思った。
- 最初は簡単だと思っていたけど今回の授業は知らないことが多かったんだ。
- 最後の我々が引っかかりそうなインチキの話がおもしろい。
|
-
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|